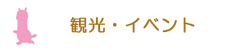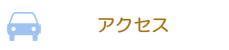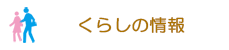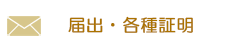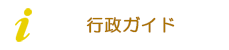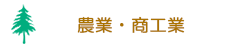父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための国の制度です。
令和6年11月以降における制度改正について
1.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
(単位:万円)
|
|
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
||||||
|
扶養する 児童等の数 |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
| これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
| 0 | 122 | 142 | 49 | 69 | 311.4 | 334.3 | 192 | 208 |
| 1人 | 160 | 190 | 87 | 107 | 365 | 385 | 230 | 246 |
| 2人 | 215.7 | 244.3 | 125 | 145 | 412.5 | 432.5 | 268 | 284 |
| 3人 | 270 | 298.6 | 163 | 183 | 460 | 480 | 306 | 322 |
| 4人 | 324.3 | 352.9 | 201 | 221 | 507.5 | 527.5 | 344 | 360 |
| 5人 | 376.3 | 401.3 | 239 | 259 | 555 | 575 | 382 | 398 |
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
| 令和6年10月分まで | 令和6年11月分から | |
| 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
| 一部支給 | 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定されます) |
10,740円~5,380円
(所得に応じて決定されます) |
※令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
対象者
次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を育成される家庭(ひとり親)に支給されます。また、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
認定請求手続きについて
手当を受けるには、健康福祉課こども家庭グループ窓口で「児童扶養手当認定請求書」に次の書類を添えて提出して下さい。
- 印鑑
- 請求者の戸籍謄本(離婚年月日の記載があるもの)
- 児童の戸籍謄本(児童が請求者以外の戸籍謄本に入って場合のみ)
- 振込先の通帳の通し
- 前住所地の所得証明書(剣淵町へ転入してきた方のみ必要です。)
- 請求者のマイナンバーの確認に必要なもの(番号確認書類と身元確認書類の2種類)
請求者の番号確認書類及び身元確認書類
児童及び扶養義務者の番号確認書類
1.番号確認書類・・・ 通知カードや個人番号カード
2.身元確認書類・・・運転免許証等(個人番号カードの場合必要なし) - その他必要書類(請求者の事情によって違いますので、事前に窓口にご相談ください。)
手当の支払い時期
- 請求内容は、北海道において審査され、約2カ月後に認定がされます。
- 認定を受けると、請求した日の属する月の翌月から支給月(1・3・5・7・9・11月)の前月分までの2ヵ月分の手当が、支給月の11日に支給され、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。ただし、11日が土日祝日の場合は、その前日になります
手当の額
★令和6年11月以降の月額は、次のとおりです。
| 第1子 | 第2子以降 | |
| 全部支給 | 45,500円 | 10,750円を加算 |
| 一部支給 | 10,740~45,490円 | 5,380~10,740円を加算 |
★令和7年4月以降の月額は、次のとおりです。
| 第1子 | 第2子 | |
| 全部支給 | 46,690円 | 11,030円を加算 |
| 一部支給 | 11,010~46,680円 | 5,520~11,020円を加算 |
○一部支給額(手当月額)=46,690円-支給停止額
支給停止額(10円未満四捨五入)=(受給者の所得額<*1>-所得制限限度額<*2>)*
0.0256619
○第2子加算額=11,030円-支給停止額
支給停止額(10円未満四捨五入)=(受給者の所得額<*1>-所得制限限度額<*2>)*
0.0039568
<*1>収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
<*2>所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
支給制限
手当を受ける方の前年の所得が扶養親族数に応じて下表の額以上である場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は手当の全部又は一部の支給が停止されます。
また手当を受ける方の配偶者・生計を同じくする扶養義務者(父母、兄弟、姉妹など)の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部の支給が停止されます。
所得制限限度額表
| 扶養親族の数 | 請求者(本人) | 扶養義務者(父母、兄弟、姉妹、 配偶者、孤児等の養育者など) |
|
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0 人 | 490,000 | 1,920,000 | 2,360,000 |
| 1 人 | 870,000 | 2,300,000 | 2,740,000 |
| 2 人 | 1,250,000 | 2,680,000 | 3,120,000 |
| 3 人 | 1,630,000 | 3,060,000 | 3,500,000 |
| 4 人 | 2,010,000 | 3,440,000 | 3,880,000 |
| 5 人 | 2,390,000 | 3,820,000 | 4,260,000 |
| 6人以上 | 以下、380,000円ずつ加算 | 以下、380,000円ずつ加算 | 以下、380,000円ずつ加算 |
(所得制限限度額表の見方は)
受給者の収入から所得税法に基づく給与所得控除等を控除し、養育費のある方はその8割
相当額を加算した所得額と上表の額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいず
れかに決定されます。次の場合は、該当する所得制限限度額にそれぞれに定める額が加算
されます。
(限度額に加算されるもの)
- 請求者本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族の税控除がある場合 10万円 / 人
特定扶養親族の税控除がある場合 15万円 /人 - 孤児等の養育者、配偶者及び父母、兄弟、姉妹など扶養義務者の老人扶養親族の税控除がある場合。ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く。 6万円 /人
届け出の内容が変わった場合
次のような場合は、健康福祉課こども家庭グループへ届けて下さい。
- 対象児童が増えたとき
- 対象児童が減ったとき
- 受給資格がなくなったとき
- 受給者が死亡したとき
- 証書を紛失したとき
- 町内で転居したとき
- 町外へ転出したとき
- 氏名を変更したとき
受給資格の喪失
- 手当を受けている母が婚姻したとき
- 手当を受けている母が男性と同居したとき(事実婚)
- 児童が施設に入所したとき
- その他、児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)とき など
児童扶養手当法の改正に伴う手続き
児童扶養手当法の改正により、手当を受けてから5年以上経過する方(ただし、8歳未満の児童がいる場合を除く)は平成20年4月から手当の受給額が1/2に減額されます。
なお、就業しているなど一定の要件を満たす場合には健康福祉課こども家庭グループへ届出をすることによって、平成20年4月以降も引き続きそれまでと同額の手当を受給することができます。