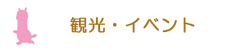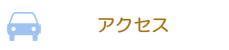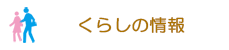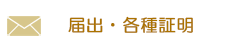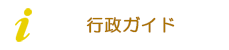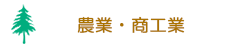名寄保健所における主な感染症の発生動向
2025年第26週(6月23日~6月29日)
| 第26週 | |
| 警報レベル | 伝染性紅斑、水痘 |
| 注意報レベル※ | 発表はありません。 |
「警報」は「大きな流行が発生または継続しつつあると疑われること」を示します。
「注意報」は流行の発生前であれば、「今後、4週間以内に大きな流行が発生する可能性が高いこと」、流行の発生後であれば、「流行が継続している」と疑われることを示します。
※注意報は、インフルエンザ、水痘、流行性耳下腺炎のみ
インフルエンザは、流行時期に合わせて、毎年、第36週(8月末~9月初旬)から翌年の第35週までの1年間をインフルエンザシーズンとして報告しています。
上記の感染症発生動向は、定点報告対象の感染症であり、あらかじめ指定した医療機関からの患者数の報告をもとに集計し、分析して報告している情報です。
北海道の感染症の発生動向
北海道の主な感染症の発生動向については、こちらでご確認ください。
道感染症対策課 HP https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kst/149369.html
剣淵町子ども・子育て支援会議での議論を経て、剣淵町こども計画が成案となりました。
令和6年10月から児童手当制度が変わります
令和6年6月12日に公布された、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)により、令和6年10月分の児童手当から、制度の内容が変わります。
制度改正の内容について
・所得制限の撤廃
(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。)
・支給期間を中学生から高校生年代まで延長
(高校生年代とは、18歳を達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。)
・支払い月を年3回から年6回に増加
(偶数月での支払いになります。)
改正前後の比較表
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
| 支給対象 | 15歳に達した最初の年度末(中学生)まで | 18歳に達した最初の年度末(高校生年代)まで |
| 所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
| 支給月額 | ・3歳未満 一律15,000円
・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律 5,000円 ・所得上限以上 支給なし |
・3歳未満
第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~高校生年代(18歳に達する日以後の 最初の3月31日まで) 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
| 第3子以降の要件 | 18歳に達する日以後の最初の3月31にまでの養育している子のうち、第3子以降 | 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、第3子以降 |
| 支給時期 | 3回(6月、10月、2月)
(各前月までの4か月分を支給) |
6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支給) |
※22歳に達した日以降の最初の3月31日までの養育する子(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
(例)20歳、16歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます(月額40,000円)。
また、制度改正により引き続き児童手当を受給される方、又は新たに受給対象になると見込まれる方は、必要な手続きに関して個別に通知いたします。
申請が必要な方・申請方法について
以下の方は申請が必要です。なお、ご夫婦の場合、生計を担う程度の高い方(原則所得の高い方)が申請者となります。離婚協議中やDV被害により配偶者と別居している場合は、児童と同居されている方が申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※公務員で対象者の方は、勤務先へご相談ください。
児童手当または特例給付を受給中の方
・令和6年9月上旬に町内回覧で送付する制度改正に係る周知文書に記載されている支給対象児童以外に支給対象となる児童がいる方
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当の世話および生計費の負担を行っており、かつ、その児童とと支給対象児童の合計人数が3人以上になる方
〇申請に必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)
・支給対象となる児童が別居している場合は、その児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当および生計費の負担を行っており、かつ、その児童と高校生年代までの支給対象児童の合計人数が3人以上になる方は、大学生年代の児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
児童手当・特例給付を受給していない方
・所得が所得上限限度額以上になったことにより、現在児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童のみを養育している方
〇申請に必要なもの
・窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)
・申請者および配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・申請者の健康保険証(またはその写し)
・児童手当の振込先の銀行口座の通帳またはキャッシュカード(請求者名義のもの)
・支給対象となる児童が別居している場合は、その児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
・平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(大学生年代)へ監護相当の世話および生計費の負担を行っており、かつ、その児童と高校生年代までの支給対象児童の合計人数が3人以上になる方は、大学生年代の児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
申請方法
健康福祉課こども家庭グループ窓口にて申請を行ってください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
※期限までに申請した方は、令和6年12月10日(火曜日)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。期限までに申請された方で支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に審査結果に係る通知を郵送します。申請は、令和7年3月31日(月曜日)まで猶予期間を設けています。猶予期間中に申請した方には、令和6年10月分に遡及して児童手当が支給されます。
申請が不要な方
・児童手当または特例給付を受給中の方で、監護している児童全員(高校生年代の児童を含む。)が剣淵町からの児童手当または特例給付の支給対象児童もしくは要件対象児童に登録されており、かつ、上記「申請が必要な方」の「イ」に該当しない方
(注意1)上記「オ」に該当する方は、申請は不要です。
(注意2)制度改正により支給額に変更がある方には、令和6年12月上旬頃を目途に支給額変更に係る通知を郵送します。
お問い合わせは
健康福祉課こども家庭グループ 0165-34-3955まで
完了期(12~18か月)
・準備中です
お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955
・準備中です
中期(7~8か月)
・準備中です
お問い合わせ 健康福祉課 電話0165-34-3955
初期(5~6か月)
<おかゆの目安>
・5カ月~(離乳食開始1か月ごろ) 10倍がゆ 米1:水10
・6か月~ 7倍がゆ 米1:水7
・7か月~ 5倍がゆ 米1:水5
・10か月前後ごろ 軟飯 米1:水3
☆家族のごはんと一緒におかゆもついでに作ってみましょう!
※パラフィン紙=クッキングシート(クッキーを焼く時などに使うツルツルの
シート)
☆かぼちゃが手に入りにくい時期は冷凍かぼちゃがお勧めです。
☆冷凍にんじんは、冷凍する前に炊飯器でおかゆと一緒に蒸したり(詳しくは
「炊飯器で離乳食」参照)、電子レンジでラップをして500w3分程度過熱して
冷ましてから冷凍しましょう。
☆「冷凍野菜で離乳食(うらごし)」は離乳食初期(5~6か月)限定の裏ワザです。
離乳食中期(7か月)以降は柔らかく煮込んで刻みましょう!
☆離乳食の指針が2019年変更になり、離乳食初期(5〜6ヶ月)から卵黄を
与えられるようになりました。
こちらでは初めて与える卵の調理方法について紹介しています♪